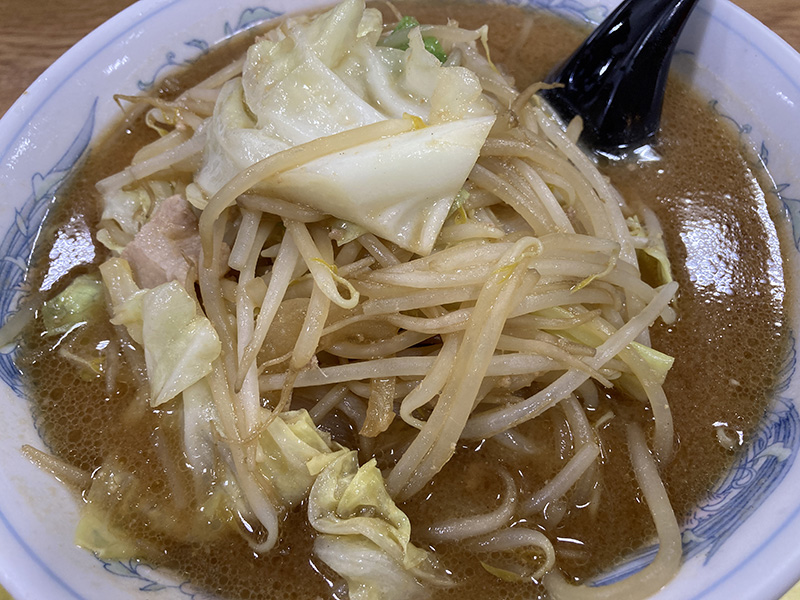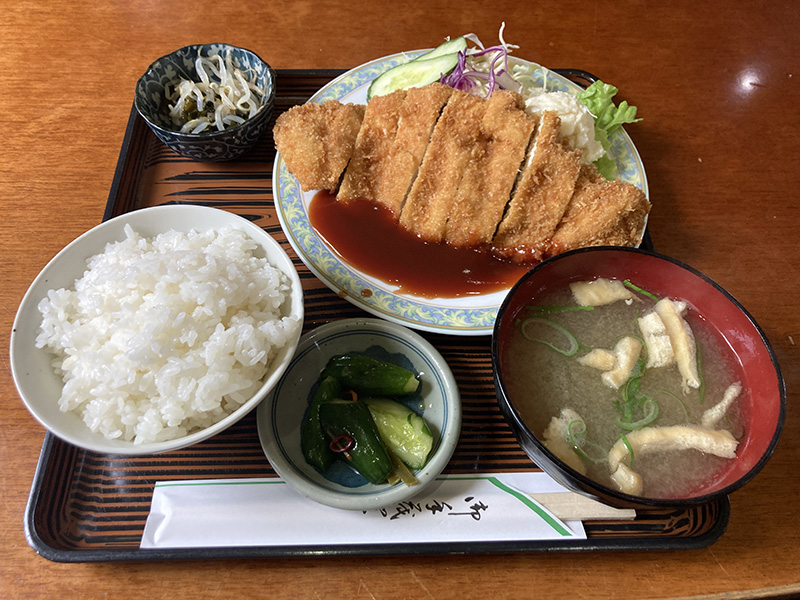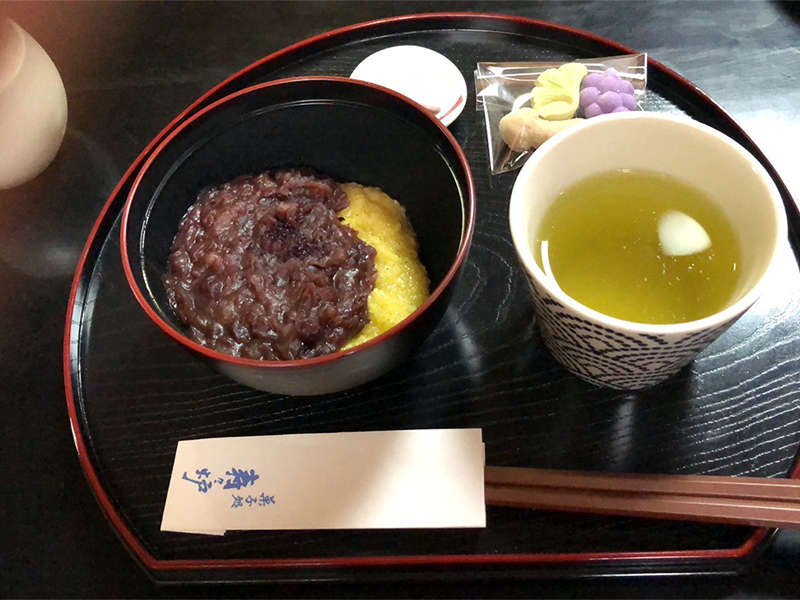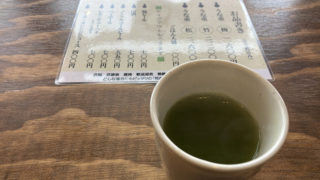青森県弘前市大字下白銀町1、弘前公園。別名は、鷹揚公園(おうようこうえん)、鷹揚園(おうようえん)。面積は約48.9haです。園内には、弘前城天守(史料館)、弘前市立博物館、弘前市民会館、弘前城植物園があります。春には約50種、2,600本の桜が咲く名所です。
南内門(ミナミウチモン)は、三の丸から杉の大橋を渡ってすぐにあります。

弘前公園、南内門
弘前公園、未申櫓 (ヒツジサルヤグラ)、櫓の名前は、天守から見た方角を12支で示したもので、未申は南西に当たります。

弘前公園、未申櫓 (ヒツジサルヤグラ)
旧藩士の菊池楯衛から1882年(明治15年)に寄贈されたもので、現存するソメイヨシノでは日本最古のものです。弘前公園のソメイヨシノは樹齢100年を越すものが300本以上あります。与力番所 (よりきばんしょ)は、上級武士に仕えていた人々のことを与力といい、その与力が見張り役として警備をした詰所のことです。

与力番所と日本一古いソメイヨシノ
東内門の周辺には、正徳桜やカスミザクラ、内側には日本最古のソメイヨシノなどがあります。

弘前公園、東内門
西濠の春陽橋 (シュンヨウバシ)は、1932年(昭和7年)、市民の通行の利便性のために架橋されました。

春陽橋
弘前公園、鷹丘橋は、内濠を隔て、本丸と北の郭に架かる橋です。

弘前公園、鷹丘橋
弘前公園の正面玄関です。周辺には、弘前市役所、弘前市図書館などがあります。

弘前公園、追手門
東門は、昭和28年(1953年)に、重要文化財指定されました。

弘前公園、東門
北方の守護神として玄武という亀の神様がいたとされており、 北側にある門の別名が亀甲門とされたのは、この伝説に由来していると言われています。

弘前公園、北門(亀甲門)
東門は、昭和28年(1953年)に、重要文化財指定されました。

弘前公園、東門
丑寅櫓 (ウシトラヤグラ)は、城郭に取りつく敵への攻撃や物見のために造られました。櫓の方角は12支を示したもので、丑寅は北東に当たります。

二の丸丑寅櫓と八重桜
秋の紅葉シーズン、敷き詰められた落ち葉を踏みしめながらの散歩道。疲れたらベンチに座ります。

紅葉の弘前公園
弘前公園は、青森県弘前市にある公園で、弘前城の敷地に広がっています。
弘前城は、江戸時代に築かれた三層の天守が現存する貴重な建築物です。
弘前公園は、春には約50種、2,600本の桜が咲く名所としても有名で、毎年「弘前さくらまつり」が開催されます。秋には紅葉も美しく、四季折々の自然を楽しめます。

二の丸辰巳櫓(にのまるたつみやぐら)
青森県弘前市、弘前公園、二の丸辰巳櫓。 二の丸辰巳櫓(にのまるたつみやぐら)は、弘前公園にある弘前城の櫓(やぐら)の一つです。 櫓とは、城郭に取りつく敵への攻撃や物見のために造られた塔のような建物です。 二の丸辰巳櫓は、 […]

藤田記念庭園、洋館
青森県弘前市上白銀町8-1、藤田記念庭園。 弘前公園に隣接し、弘前市出身の藤田謙一氏が大正八年に別邸を構える際、つくらせた庭園です。 洋館は、1921年(大正10年)に建てられた木造モルタル2階建ての建物です。 現在は、 […]

お盆、牛馬の飾り
お盆には、ご先祖様の霊が家に戻ってくるという考えから、なすときゅうりで馬と牛を作ってお供えする風習があります。 馬と牛は、あの世とこの世を行き来する乗り物として見立てられています。 馬は足の速いきゅうりで、牛は足の遅いな […]

小沢小学校創立百年記念の碑
青森県弘前市小沢御笠見9、小沢運動広場内、小沢小学校創立百年記念の碑。 1976年、昭和51年6月5日に建立されました。 小沢小学校は、1876年、明治9年9月19日創立しました。 小沢小学校は、1976年、現在地、青森 […]
青森県中津軽郡西目屋村、暗門滝(あんもんのたき)は、岩木川上流の白神山地内の暗門川にあります。
3つの滝から構成されています。
上流側から高さ42メートルの第一の滝
その200メートル下流に同37メートルの第二の滝
さらに160メートル下流に同26メートルの第三の滝があります。

鷹丘橋、弘前公園
鷹丘橋とは、弘前公園の内濠に架かる橋で、本丸と北の郭を結んでいます。 鷹丘橋という名は、弘前城の旧名である鷹丘城(高岡城)にちなんだものと思われます。 この橋は1670年(寛文10年)、4代藩主 信政 が母の屋敷のある北 […]

鷹丘橋、弘前公園
鷹丘橋とは、弘前公園の内濠に架かる橋で、本丸と北の郭を結んでいます。 鷹丘橋という名は、弘前城の旧名である鷹丘城(高岡城)にちなんだものと思われます。 この橋は1670年(寛文10年)、4代藩主 信政 が母の屋敷のある北 […]