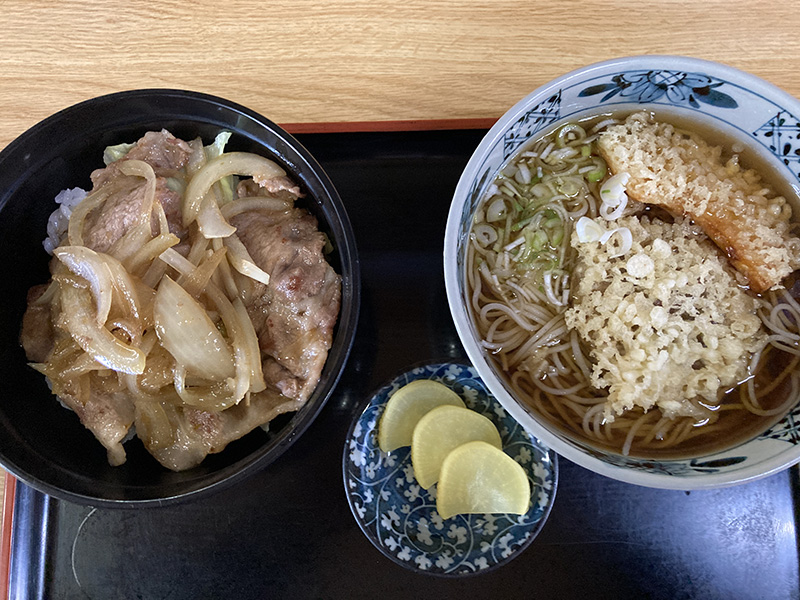津軽の歴史を学ぼう!過去がわかれば、未来も開けてきます。歴史は人々が生きた証です。
津軽は、655年「日本書紀」に、「津苅」「東日流」「津刈」「都加留」と表記されています。
中世には「平賀郡(津軽平賀郡)」「鼻和郡(津軽鼻和郡)」「田舎郡(津軽田舎郡)」に分けられ「津軽三郡」と言われた。
弘前公園。別名は、鷹揚公園(おうようこうえん)、鷹揚園(おうようえん)。
鎌倉時代は北条得宗領として安東氏などが支配したが、14世紀になると、南部氏が支配するようになる。
戦国時代に津軽氏が支配した。近世になると、それまでの「平賀郡」「鼻和郡」「田舎郡」の3郡がまとめられて「津軽郡」となる。
明治維新のあと、青森県の一部となる。1878年(明治11年)、東津軽郡・西津軽郡・南津軽郡・北津軽郡・中津軽郡に分けられた。

弘前公園
青森県弘前市大字下白銀町1、弘前公園。別名は、鷹揚公園(おうようこうえん)、鷹揚園(おうようえん)。面積は約48.9haです。園内には、弘前城天守(史料館)、弘前市立博物館、弘前市民会館、弘前城植物園があります。春には約 […]

岩木山の歴史
岩木山は標高1625mの円錐形の成層火山で、山頂は三つの峰にわかれており、弘前側からみた右が巌鬼山(岩鬼山)、左が鳥海山とされています。 岩木山は、青森県の最高峰で、津軽富士とも呼ばれる美しい山です。 岩木山は約70万年 […]

岩木山神社
岩木山神社(いわきやまじんじゃ) 岩木山神社は、青森県弘前市にある神社で、岩木山の南東麓に鎮座しています。 入り口から参道、楼門、拝殿、本殿。そして奥の院は岩木山山頂にあります。津軽富士とも呼ばれる美しい岩木山のふもとに […]

高山稲荷神社、千本鳥居
青森県つがる市牛潟町鷲野沢147−1、高山稲荷神社。 五穀豊穣、海上安全、商売繁盛の神様として大変ご利益のある神社です。 千本鳥居は、参拝者の奉納によって建てられた鳥居で、願いが「通る」という語呂合わせから生まれた信仰だ […]

八甲田山周辺
八甲田山(はっこうださん)は、青森市の南側にそびえる複数火山の総称で日本百名山の一つ。「八甲田山」と名がついた単独峰は存在せず、18の成層火山や溶岩円頂丘で構成される火山群です。 遭難し、直立したまま仮死状態で発見された […]

津軽の石碑
石碑を見ると古の人を思う。時代を超え語りかけるものがある。風雪に削られようとも、そこにありつづけるだろう。新しく建てられる石碑もあれば、人々に忘れ去れそうな石碑もある。 青い山脈歌碑。 西条八十作詞「若くあかるい 歌声に […]
津軽の歴史を学ぼう! 過去がわかれば、未来も開けてきます。歴史は人々が生きた証です。
津軽は、655年「日本書紀」に、「津苅」「東日流」「津刈」「都加留」と表記されています。
中世には「平賀郡(津軽平賀郡)」「鼻和郡(津軽鼻和郡)」「田舎郡(津軽田舎郡)」に分けられ「津軽三郡」と言われた。

慧眼(けいがん)とは
慧眼(けいがん)とは、「物事の本質を鋭く見抜く力」のことを指します。 仏教用語では、「えげん」とも読み、一切の事物を空であると見通す智慧の目を意味します。 類語には「先見の明」や「洞察力」などがあります。 対義語には「節 […]

鷹丘橋、弘前公園
鷹丘橋とは、弘前公園の内濠に架かる橋で、本丸と北の郭を結んでいます。 鷹丘橋という名は、弘前城の旧名である鷹丘城(高岡城)にちなんだものと思われます。 この橋は1670年(寛文10年)、4代藩主 信政 が母の屋敷のある北 […]