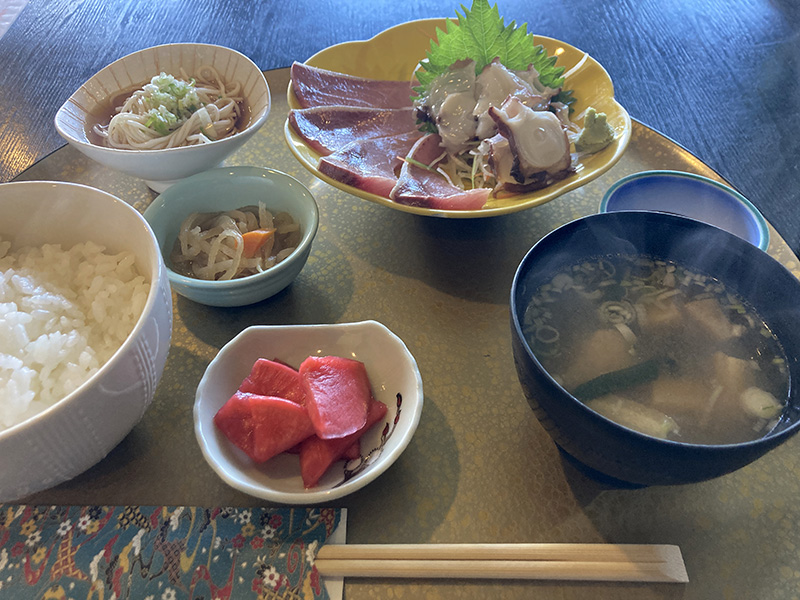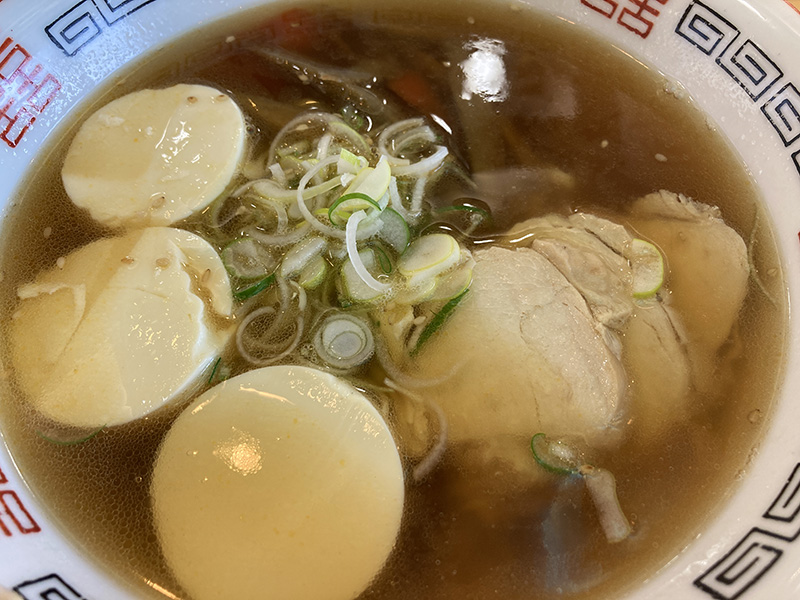土屋御番所
青森県東津軽郡平内町土屋鍵懸56、ほたて広場内、土屋御番所。
土屋御番所は、江戸時代に黒石藩が設置した口留番所のことです。
口留番所とは、領地の境界にある検問所で、通行人の身分や目的を調べたり、不審者や密輸品を取り締まったりする役目を果たしていました。
土屋御番所は、黒石藩初代藩主津軽十郎左衛門信英が、明暦2年(1656年)に領地境界警備のために設置しました。
黒石藩は、奥州街道沿いにある小さな藩で、領地は約3万石でした。
土屋御番所は、黒石藩平内領の西側にあたる領境にありました。
ここは、南部藩との国境でもありました。
土屋御番所は、奥州街道を通る人々を監視し、黒石藩の安全を守っていました。
明治維新となり、領地制度が廃止されると、土屋御番所も必要なくなりました。
明治2年(1869年)6月に廃止されました。
現在は、平内町の土屋地区にその跡が残っています。
そこには、土屋御番所の由来や歴史を説明する看板が立っています。

土屋御番所由来

太宰治記念館・斜陽館
青森県五所川原市金木町朝日山412-1、太宰治記念館・斜陽館。 斜陽館は、太宰治の生家であり、1907年(明治40年)に父・津島源右衛門によって建てられた豪邸です。 和洋折衷の建築で、国の重要文化財に指定されています。 […]

赤田のアカマツ
青森県北津軽郡板柳町大字赤田字松下、赤田のアカマツ。 赤田には、アカマツという名前の古木があります。 板柳町の指定文化財第八号になっています。 このアカマツは、樹齢約300年、樹高約12.5メートル、幹周囲約3.55メー […]

羽州街道
青森県青森市浪岡増館から下十川間、羽州街道。 羽州街道は、江戸時代に整備された脇往還(五街道に次ぐ街道)の一つです。 奥州街道から福島県の桑折で分かれ、宮城県を経て奥羽山脈を越え、山形県、秋田県を北上し、青森県の油川で奥 […]
青森県弘前市銅屋町、最勝院五重塔。
国の重要文化財指定の五重塔としては日本最北端に位置。
寛文7年(1667年)に完成した旧大円寺の塔で、総高31.2メートルである。
津軽藩3代藩主津軽信義、4代津軽信政の寄進により、前後10年以上をかけて建立されました。

地球の重力から逃れるために!
宇宙速度とは、地球や太陽などの重力から逃れるために必要な最小の速度のことです。 宇宙速度には第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度の3種類があります。 第一宇宙速度は、地球表面すれすれを人工衛星として飛行するために必要 […]