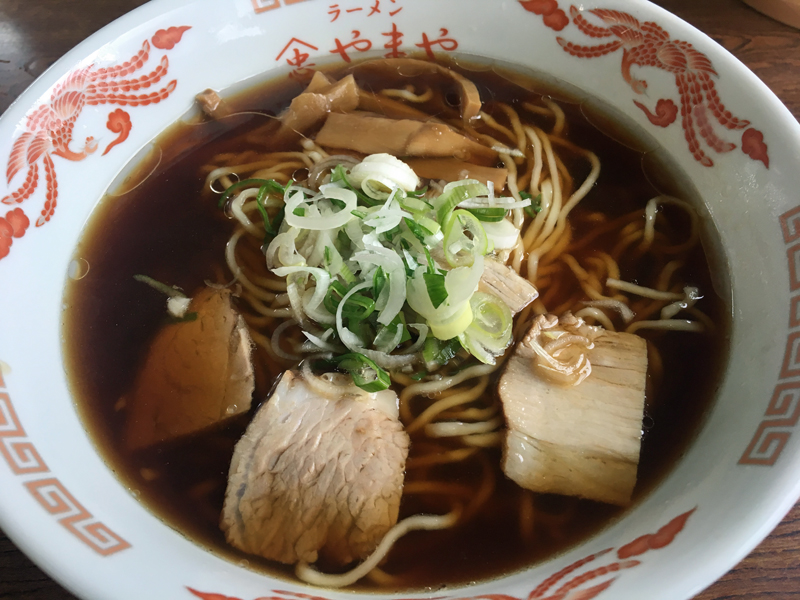三内丸山遺跡
青森県青森市大字三内字丸山305、三内丸山遺跡。
三内丸山遺跡は、縄文時代の大規模な集落跡です。
約5900年前から4200年前にかけて、河岸段丘上に多数の竪穴住居や高床式倉庫、柱列建物などが建てられていました。
1997年に国の特別史跡に指定されました。

三内丸山遺跡、大型掘立柱建物
大型掘立柱建物は、地面に穴を掘り、柱を建てて造った建物のことです。
縄文時代には、拠点集落の中心的な建物として用いられました。
三内丸山遺跡では、6本柱の長方形の大型掘立柱建物が発見されています。
柱穴は直径・深さとも約2mで、中に直径約1mのクリの木柱が残っていました。
高床式倉庫は、集落の周辺にある3棟あります。
縄文人が食料や道具を保管していたと考えられています。

三内丸山遺跡、大型掘立柱建物
三内丸山遺跡は、青森県青森市にある縄文時代の大規模集落跡です。
紀元前約3,900~2,200年(現在から約5,900~4,200年前)に築かれたとされており、竪穴建物や掘立柱建物、盛土、墓などが発見されています。
2021年7月27日には、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会で「縄文時代の集落遺跡群」の一部として世界遺産に登録されました。
縄文時代は、日本列島における時代区分の一つで、旧石器時代の後に当たります。
世界史では中石器時代または新石器時代に相当する時代です。
縄文時代の特徴としては、土器と弓矢の使用、磨製石器の発達、定住化の進展などが挙げられます。
縄文時代は約1万年以上にわたって続きましたが、その間には気候や自然環境、人々の生活や文化などが変化しました。
2021年7月27日には、北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録されました。

二の丸丑寅櫓、弘前公園
青森県弘前市、二の丸丑寅櫓(にのまるうしとらやぐら)は、弘前公園にある弘前城の櫓(やぐら)の一つです。 櫓とは、城郭に取りつく敵への攻撃や物見のために造られた塔のような建物です。 二の丸丑寅櫓は、二の丸の北東を守るために […]

親子石、鶴田八幡宮
青森県北津軽郡鶴田町鶴田字生松53、鶴田八幡宮。 親子石は、 古くは天保年間には祀られていたと伝承されています。 左側から父・子・母となっており 子の石だけが地面に埋まっているのは産まれて来る赤子を表しています。 夫婦円 […]

兼平天満宮(かねひらてんまんぐう)様
十二支4番目の卯年の天満宮 守り本尊:文珠菩薩様 呼称:兼平天満宮(かねひらてんまんぐう)様 場所:青森県弘前市兼平山下林添106 慶長8年(1603年)、津軽藩主津軽為信が再興して社殿を修理し、悪病退散を願ったといいま […]

弘前公園の散策コース
弘前公園は、弘前城を中心とした歴史的な公園で、桜の名所としても有名です。 弘前公園には、天守や櫓、門、橋などの城郭遺構が多く残っており、藩政時代の雰囲気を感じることができます。 おすすめ弘前公園の散策コース 弘前城の1棟 […]
花が咲くまで7年前後の期間が必要とされています。
カタクリ(片栗)は、ユリ科カタクリ属に属する多年草。
カタクリの花には、「初恋」「寂しさに耐える」という2つの花言葉があります。
カタクリの花は、種が根付いてから、花が咲くまで7年前後の期間が必要とされています。
また、多年草ではあるものの、花を咲かせられるのは7回程度とも言われています。

鷹丘橋、弘前公園
鷹丘橋とは、弘前公園の内濠に架かる橋で、本丸と北の郭を結んでいます。 鷹丘橋という名は、弘前城の旧名である鷹丘城(高岡城)にちなんだものと思われます。 この橋は1670年(寛文10年)、4代藩主 信政 が母の屋敷のある北 […]