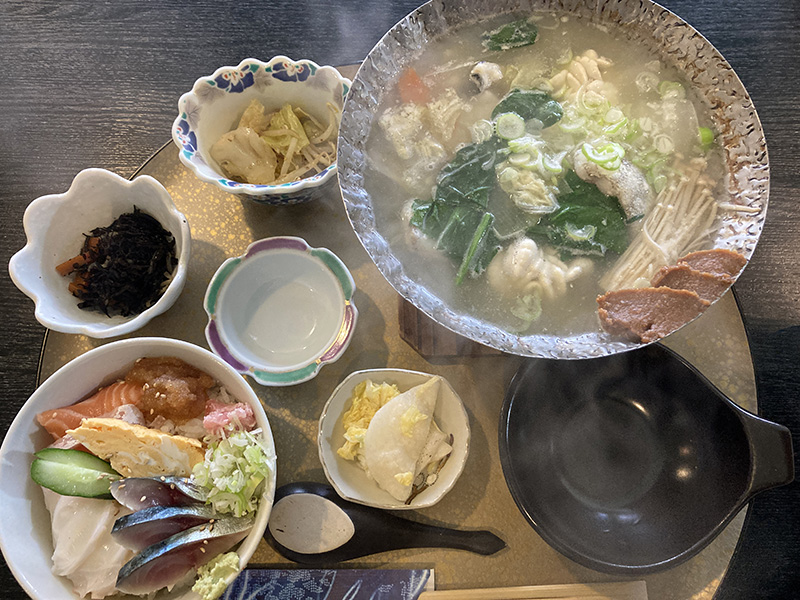赤田のアカマツ
青森県北津軽郡板柳町大字赤田字松下、赤田のアカマツ。
赤田には、アカマツという名前の古木があります。
板柳町の指定文化財第八号になっています。
このアカマツは、樹齢約300年、樹高約12.5メートル、幹周囲約3.55メートルの巨木で、地上1.5メートルのところで二股に分かれています。
その股のところからニワトコが生えています。

赤田のアカマツ

赤田のアカマツ
アカマツは、日本をはじめとする東アジアに広く分布するマツ科マツ属の常緑針葉樹です。
赤みを帯びた樹皮や細く短い葉が特徴で、別名メマツ(女松)とも呼ばれます。
アカマツは乾燥や貧栄養に強く、岩場や尾根沿いなどに生育します。
また、菌類と共生して菌根を形成し、マツタケなどのキノコを育てます。
アカマツは春に赤褐色の新芽を出し、4月から5月にかけて雌雄の花を咲かせます。
翌年の秋には卵形の毬果(松ぼっくり)が熟し、種子を散らします。
アカマツは建築材や木炭材料として利用されるほか、盆栽や苔玉などの観賞用としても栽培されます。

赤田のアカマツ
アカマツの花言葉は、細くて柔らかな葉と、赤褐色の幹が女性らしいしなやかさを連想させることから、「気高さ、気品」という花言葉がつけられました。
また、松と同様に、樹齢が長いことから「不老長寿」という意味もあります。

イトラン(糸蘭)
イトランは、リュウゼツラン科の植物で、ユッカとも呼ばれます。 白い花を咲かせる常緑低木で、耐寒性や耐暑性があります。 イトランにはいくつかの種類がありますが、日本でよく見られるのはセンジュラン(Yucca aloifol […]

ジニア(百日草)、庭
ジニアはキク科の一年草で、百日草とも呼ばれます。 メキシコを中心に南北アメリカに原産し、色や形の豊富な花を長期間咲かせます。 ジニアの花言葉は、「不在の友を思う」「注意を怠るな」です。 これは、ジニアの開花期間が長いこ […]

ヒメザクラ
ヒメザクラの原産は中国ですが、ヨーロッパに渡った後日本に入ってきました。 全体に白い粉がつくことから化粧桜とも呼ばれています。 長期間様々な色の花が咲くため、花壇に植える人気の植物です。

ジャノメクンショウギク、庭
ジャノメクンショウギク(蛇の目勲章菊)は、南アフリカ原産のガザニアの園芸品種で、キク科ガザニア属の半耐寒性多年草です。 花の形が勲章のように見えることから、この名前がつけられました。 花色は白や黄色、オレンジ、赤などの鮮 […]