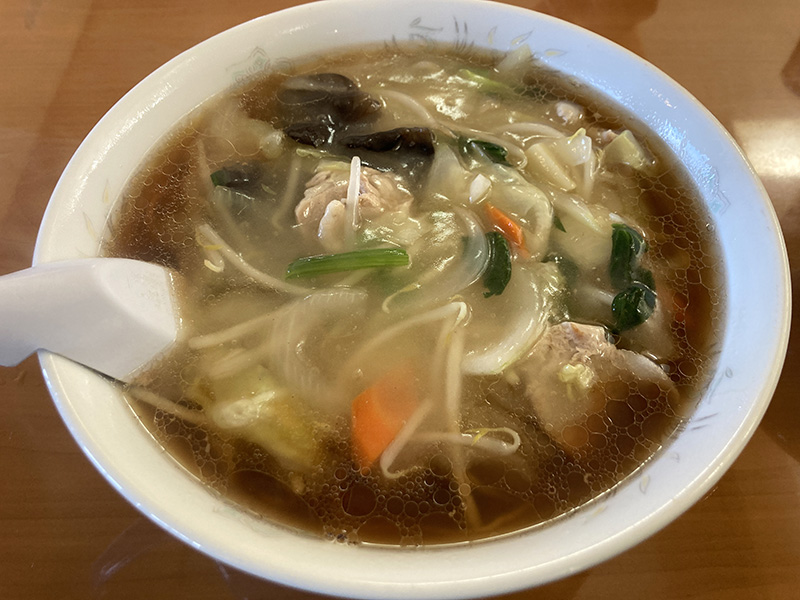弥生画、鶴田八幡宮
青森県北津軽郡鶴田町鶴田字生松53、鶴田八幡宮。
弥生画は、五穀豊穣を願って、穀物の種子を一粒ずつ額に貼り付けて作る絵のことです。
全国で唯一、青森県鶴田町で継承されている伝統芸術です。

弥生画、鶴田八幡宮
弥生画の歴史は、天明の大飢饉の時代にさかのぼります。
当時、食糧不足に苦しんだ村人たちは、残り少ない種子を持ち寄って、雨の神様に祈願したところ、翌年は大豊作になったと言われています。
それ以来、毎年元旦に弥生画を作って神社に奉納するようになりました。
弥生画の名前は、弥生時代に中国から日本に穀類や種子などが移入されたことにちなんで命名されたといわれています。

弥生画、鶴田八幡宮
弥生画には、10数種類の穀物が使われており、いっさい着色をせずに、穀物の色や形を生かして精巧な絵を描いています。
弥生画は、鶴田八幡宮や山道闇おかみ神社に奉納された後、道の駅つるたに展示されています。

弥生画、鶴田八幡宮
10数種類の穀物は、なたね、えごま、あわ、きび、マイロ、レンズ豆、稲穂、青米、うるち米、もち米、紫黒米、小豆、白小豆、緑豆、大豆、茶大豆、黒豆、トラ豆、ひまわり、スチューベンです。
きびは、イネ科の一年草で、種子を食用にする穀物の一種です。
きびには、粘りのあるもちきびと粘りの少ないうるちきびがあります。
きびは、カルシウムやマグネシウム、鉄分や食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。
きびは、白米と一緒に炊いたり、お菓子やお餅などに加工したりして食べられます。
きびは、日本では古くから親しまれており、童話『桃太郎』の作中に登場するキビダンゴは有名です。
マイロは、ソルガム(タカキビ、コウリャン、マイロ)の実を粉砕したもので、飼料やきのこ培地に使われる栄養材です。
マイロは、カルシウムやマグネシウム、鉄分や食物繊維などの栄養素が豊富に含まれており、食用としても利用できます。
マイロは、アフリカやアジアなどの暑く乾燥した地域で栽培されており、世界の穀物生産量では第5位です。
レンズ豆は、マメ科ヒラマメ属の一年草で、種子を食用にする穀物の一種です。
レンズ豆は、光学レンズのような平たい形が特徴で、皮付きと皮なしのものがあります。
レンズ豆は、鉄分や食物繊維などの栄養素が豊富で、スープやカレー、サラダなどに使われます。
紫黒米は、イネの栽培品種のうち、玄米の種皮または果皮にアントシアニン系の紫黒色素を含む品種のことです。
紫黒米は、白米に混ぜて炊くと紫色に炊き上がります。
紫黒米には、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれており、健康食や美容食として注目されています。
紫黒米は、中国や東南アジアなどで古くから栽培されてきました。
日本では、農研機構が品種改良を行い、糯種の「朝紫」や粳種の「おくのむらさき」などが育成されています。
トラ豆は、つる性のいんげんまめで、北海道で高級菜豆と呼ばれている豆の一種です。
トラ豆は、へその周りに虎のような模様があることから名付けられました。
トラ豆は、やわらかくて甘みがあり、煮豆や甘露煮などにするとおいしいです。

津軽の市町村
津軽の市町村は、青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、大鰐町、藤崎町、田舎館村、西目屋村、板柳町、鶴田町、中泊町、鰺ヶ沢町、深浦町、外ヶ浜町、平内町。 青森市(あおもりし)は、青森県の中央部に位置する市で […]

田んぼアート2023、田舎館村
青森県南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻123-1、田舎館村役場、展望台より。 田舎館村は、田んぼアートの発祥の地として有名です。 田んぼアート2023は、「門世の柵と真珠の耳飾りの少女」です。 門世の柵は、版画家、棟方志 […]

高岡の森弘前藩歴史館
青森県弘前市高岡字獅子沢128-112、高岡の森弘前藩歴史館。 弘前藩主津軽家の旧蔵品を中心とした資料を展示しており、弘前の歴史や文化を学ぶことができます。 平成30年(2018年)4月1日にオープンしました。 高岡の森 […]

藤田記念庭園、庭園
青森県弘前市上白銀町8-1、藤田記念庭園。 弘前公園に隣接し、弘前市出身の藤田謙一氏が大正八年に別邸を構える際、つくらせた庭園です。 その後、弘前市政百周年記念事業として整備し、平成3年7月に開園しました。藤田記念庭園( […]

津軽の歴史
津軽の歴史を学ぼう!過去がわかれば、未来も開けてきます。歴史は人々が生きた証です。 津軽は、655年「日本書紀」に、「津苅」「東日流」「津刈」「都加留」と表記されています。 中世には「平賀郡(津軽平賀郡)」「鼻和郡(津軽 […]
回る、回る、回る・・・・。
回転鮨には良く行きます。
でも、ひとりではなかなか行けません。
そんな時はこのスライドショーで・・・・・。
でも、お腹は一杯になりません。
逆にお腹が空くかも・・・・・。

怒る、叱るは意味がない
「怒る」とは、自分の感情を抑えられずに不満や不快なことを相手にぶつけることです。 自分のために感情を爆発させるだけで、相手に何かを伝えることはできません。 「叱る」とは、相手の非を正すために厳しく注意することです。 相手 […]