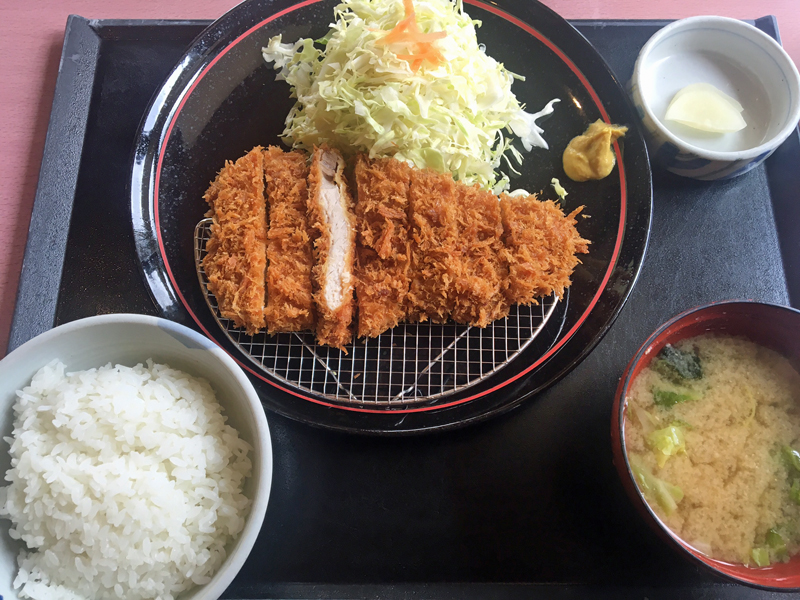しゃこちゃん
青森県つがる市には国指定重要文化財の「遮光器土偶」が出土した亀ヶ岡遺跡があり、「遮光器土偶」は「しゃこちゃん」の愛称で親しまれています。
1887年につがる市の亀ヶ岡遺跡から出土した遮光器土偶です。
遮光器土偶は縄文時代後期から晩期の集落遺跡で見つかった土人形で、目の部分が雪眼鏡(ゴーグル)のように見えることからその名が付けられました。
遮光器土偶は国の重要文化財に指定され、東京国立博物館に所蔵されています。

しゃこちゃん
遮光器土偶とは、縄文時代に作られた土偶の一種です。
目にあたる部分がイヌイットやエスキモーが雪中行動する際に着用する遮光器(スノーゴーグル)のような形をしていることからこの名称がつけられました。
遮光器土偶は主に東北地方から出土し、縄文時代晩期のものが多いです。
遮光器土偶の用途や役割については、多産や豊穣を祈願するための儀式用として使われたという説や、再生への祈りを込めたという説など、様々な説がありますが、確かなことはわかっていません。

しゃこちゃん
縄文時代は、日本における時代区分の一つで、旧石器時代の後に当たり、世界史では中石器時代または新石器時代に相当する時代です。
縄文時代は約1万6000年前から約2400年前まで続きました。
縄文時代の特徴としては、土器や弓矢の使用、磨製石器の発達、定住生活や竪穴建物の普及、貝塚や土偶などの形成などが挙げられます。
縄文時代は地域や時期によって多様な文化を展開しましたが、基本的には自然環境に適応した採集経済に基づいていました。
縄文人とは、縄文時代に日本列島全域に居住していた人々の総称で、現在の日本人やアイヌ人の祖先と考えられています。

亀ヶ岡遺跡

長勝寺三門
青森県弘前市西茂森1丁目23-8、長勝寺三門。 長勝寺三門(ちょうしょうじさんもん)は、寛永6年(1629)二代藩主信枚により建立されたものです。 岩木山神社楼門(寛永5年建立)と同じように柱を上から下までの通し柱とする […]

摺鉢山
森県弘前市大字清水富田字寺沢125、弘前りんご公園内、摺鉢山。 摺鉢山は、標高708mの人工の山です。 摺鉢山は、江戸時代に鉄砲や大砲の練習の的にするために築いた人工の山です。 山頂からは、りんご公園の全景や、近隣のりん […]

青森銀行記念館
青森県弘前市大字元長町26、青森銀行記念館。 青森銀行記念館は、明治時代に建てられた国の重要文化財に指定されている洋風建築です。 旧第五十九国立銀行の本店として使われていた建物で、白とミントグリーンの美しい外観や、金唐 […]

松尾芭蕉句碑、黒石神社
青森県黒石市市ノ町、黒石神社内、松尾芭蕉句碑。 1893年、明治二十六年建立。 句碑文は、春も稍けしき調ふ月と梅 春の夜におぼろげに照る月と咲き始めた梅の花を見て、春の気配が次第に整ってくることを感じたものです。 季語は […]

嶽きみ、柳田とうもろこし店
青森県弘前市百沢字裾野892、柳田とうもろこし店。 嶽きみとは、青森県弘前市の西部にある岩木山の麓に広がる嶽高原で栽培されるブランドとうもろこしです。 その甘さの秘密は、昼夜の寒暖差にあります。 嶽きみは地域団体商標とし […]