やる気を出すための方法
やる気とは、何かをするための動機や意欲のことです。
やる気には内発的動機と外発的動機の2種類があります。
内発的動機とは心からやりたいと思うモチベーションで、外発的動機とは他者からの報酬や評価などによって起こるモチベーションです。
やる気を出す方法には、行動アプローチ、感情アプローチ、思考アプローチの3つのアプローチがあります。
行動アプローチとは、作業興奮を利用したり、環境を変えたりすることでやる気を引き出す方法です。
感情アプローチとは、ごほうびを用意したり、ライバルと競争したりすることでやる気を盛り上げる方法です。
思考アプローチとは、作業をゲーム化したり、「誰かのために」と考えたりすることでやる気を引き出す方法です。
やる気がない人間も、やる気がある人間も、同じように存在しています。
やる気がないと感じるのは、自分にとって重要な目標が見えていないか、達成できると信じられないか、自分の能力に自信がないかのどれかだと思います。
人間は行動を起こすから「やる気」が出てくる生き物であり、面倒なときほどあれこれ考えずに、さっさと始めてしまえばいいとも言われています。
本来「やる気」というのは、行動を起こせば自然とついてくるものだということです。
ああ、今日もやる気がしないなあ。
こころ当たりがあります。
でもとにかく、やってみるか、そのうちやる気が出てくるかもしれない?

人には色んな見方がある
人にはいろんな見方があります。 偏見を持つのはやめた方がいい。 人を傷つけてはいけない。 正しいと思う心が危ない。 人は皆ほぼ、自分が正しいと思って暮らしています。 大切な人を大切にしたい。 立場の弱い人にやさしくなりた […]
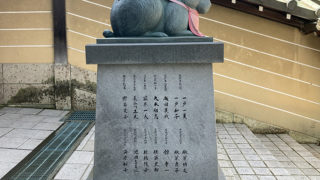
過ちて改めざるをこれ過ちという
論語、過ちて改めざるこれを過ちというとは、失敗そのものではなく、失敗をしたと気づいているにもかかわらず改めようとしないことこそが本当の過ちであるということです。 人間は誰しも完璧ではないため、間違いを犯すことはあります。 […]

馬脚を現す!
馬脚を現すとは、隠していた本性や悪事がばれることのたとえ。 馬脚は、芝居で馬の足に扮する役者のこと。 馬の足を演じていた役者がうっかり自分の姿(足)を見せてしまうことから、隠していた本来の姿が表にあらわれること、化けの皮 […]
弘前市(ひろさきし)は、日本で最初に市制施行地に指定された都市のひとつ。
弘前藩の城下町として発展し、現在も津軽地方の中心都市です。
弘前市の木として「りんご」、市の花として「さくら」を選定しています。

東内門外橋(石橋)、弘前公園
東内門外橋(石橋)は、弘前公園の中にある石造りの橋で、二の丸と三の丸を隔てる中濠に架かっています。 1848年(弘化5年)に土橋から架け替えられたもので、城内では唯一の石造りの橋です。 橋を渡るとすぐに東内門があり、その […]










